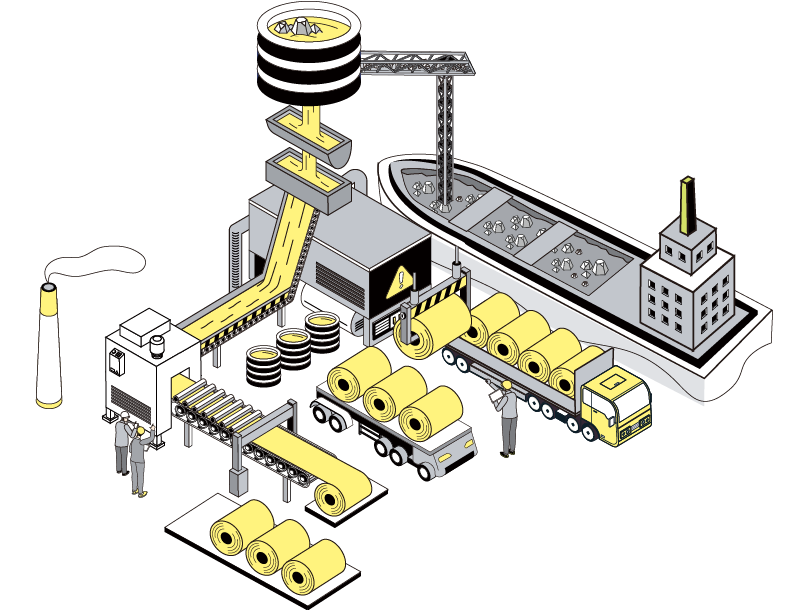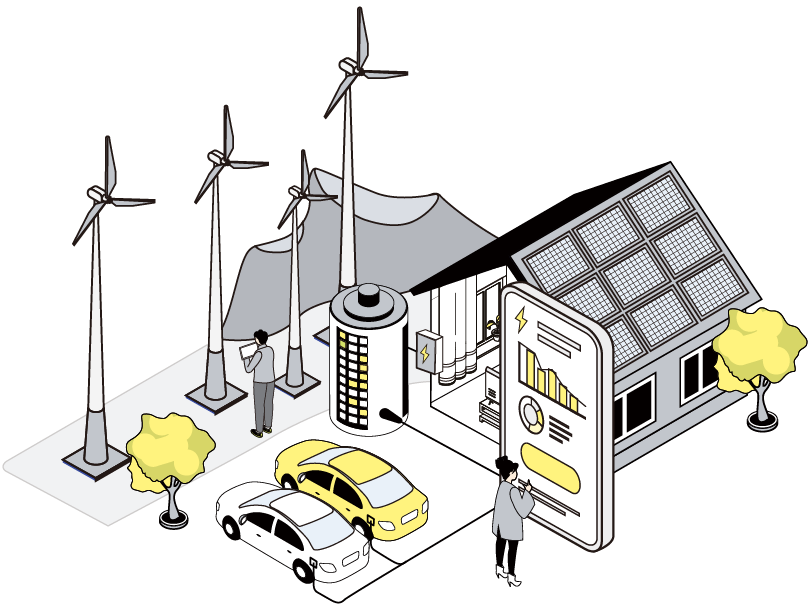自動車:生成AI/最適化分野PROJECT STORY #02
先端技術をいかにして
お客様にベストな状態で
お届けするのか
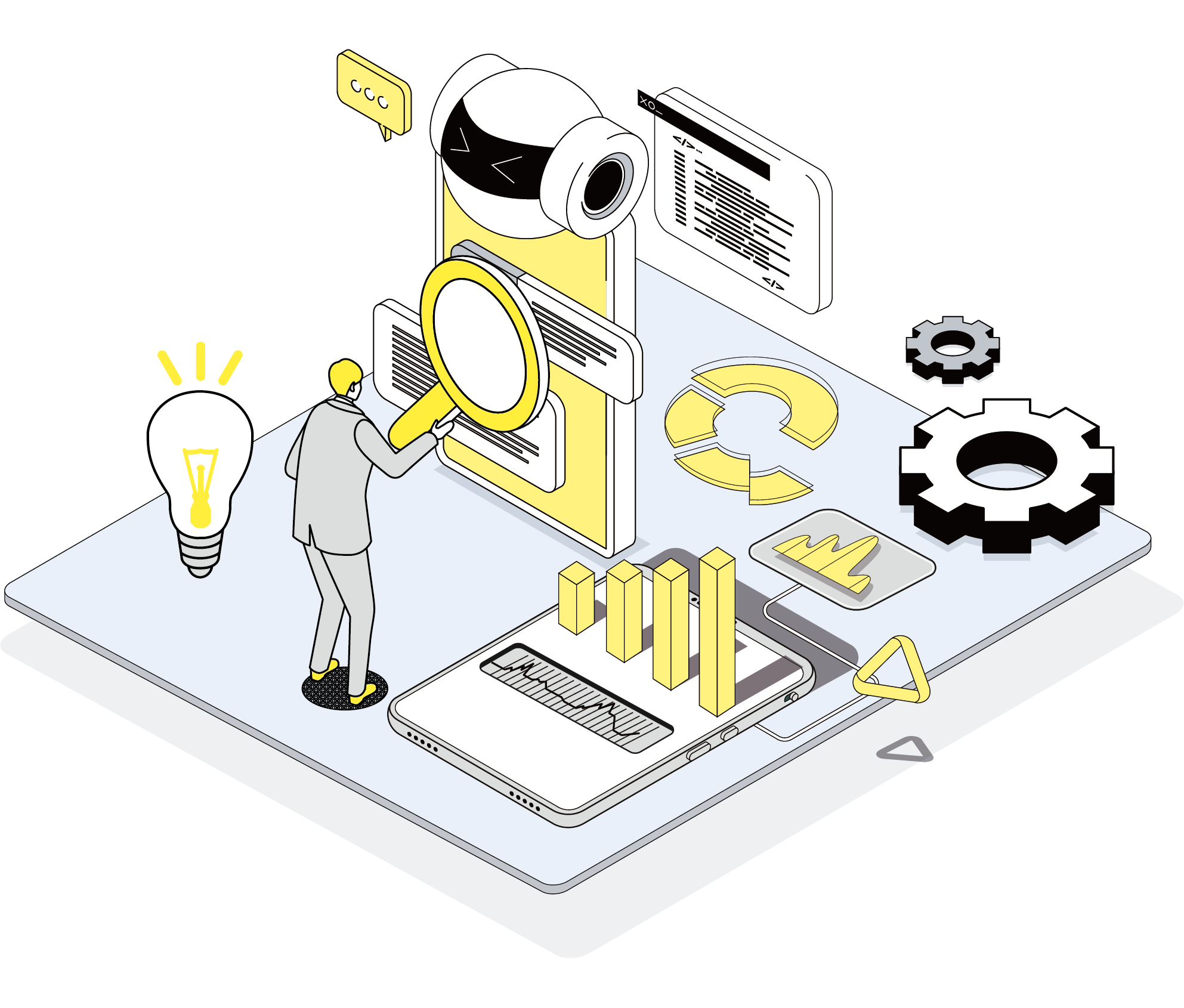
about story
生成AIの顧客適用に向けた研究開発と、生産・物流などの領域で適用した「最適化ソリューション」。いずれも顧客からのニーズが高い分野だけに挑戦のしがいがある一方で、立ちふさがる課題も多数。研究開発はゼロからのスタート、そして時代やニーズに合わせ進化し続ける最適化プロジェクト。今回は先端技術に携わる4人に話を聴いた。手法は異なっても、先端技術をより効果的に活用して幅広いお客様に貢献していきたいという熱い想いだ。
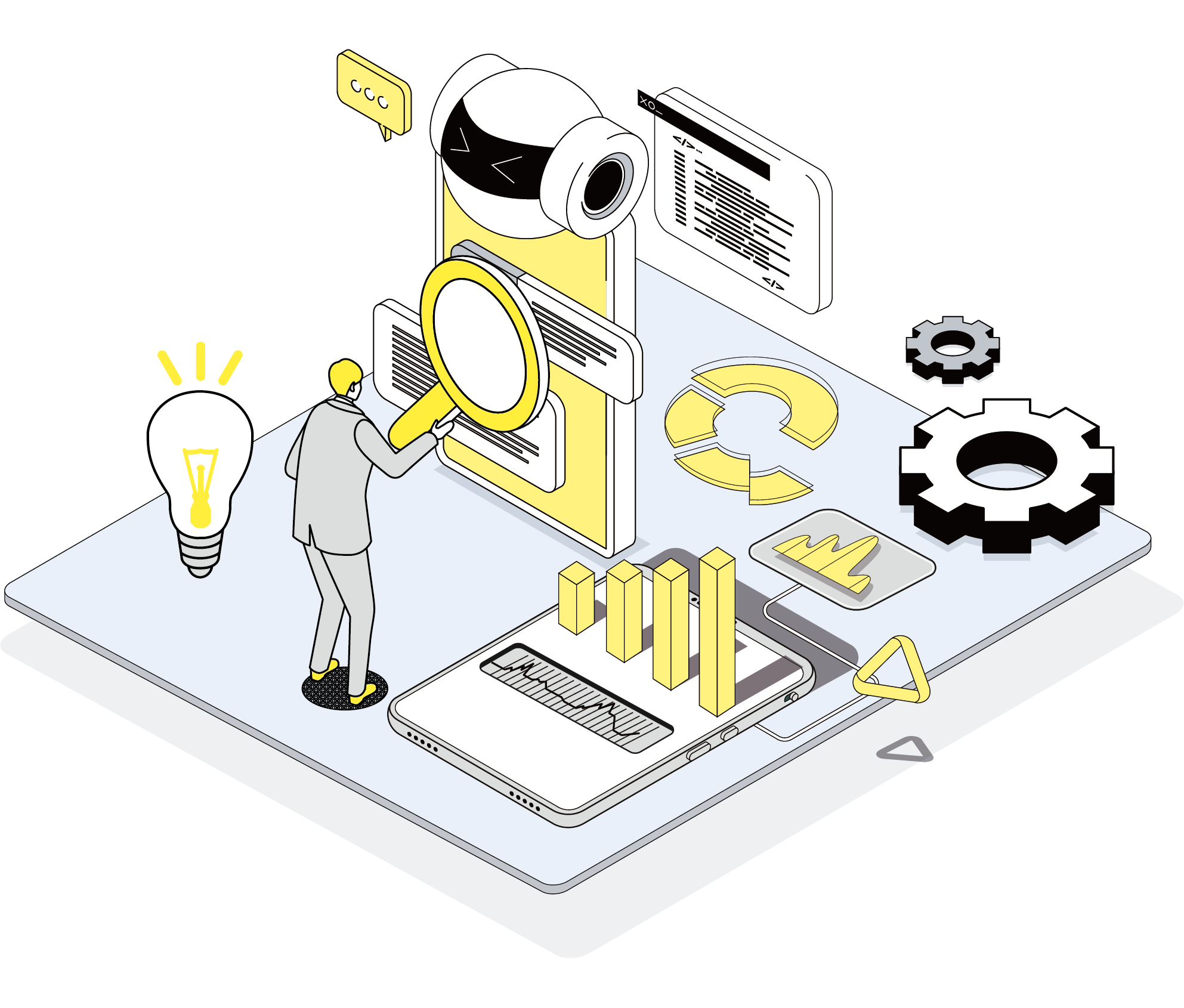
CROSS TALK MEMBER





業務ソリューション第二事業部
システムエンジニアリング第一部
T.Ozawa





業務ソリューション第二事業部
システムエンジニアリング第三部
K.Yamamoto





イノベーション推進センター
ソリューション研究開発部
R.Hoshino





イノベーション推進センター
ソリューション研究開発部
Li.S
Q.はじめに業務ソリューション事業部の Oさんと
Oさんと Yさんからお話を伺います。お二人の業務は生成AIをお客様に適用するプロジェクトなのでしょうか。
Yさんからお話を伺います。お二人の業務は生成AIをお客様に適用するプロジェクトなのでしょうか。
-

T.Ozawaさん
- 我々は普段自動車業界向けのプロジェクトに参画していますが、今回は当社の自主的な取り組みとして生成AIの活用について研究しています。
-

K.Yamamotoさん
- 生成AIの活用については大きく分けて以下の2つの方向性があります。
①システム開発における生成AI活用による生産性向上
②お客様向けシステムへの生成AIの組み込みによる新たな価値創出
このうち、私たちの取り組みは「②お客様向けシステムへの生成AIの組み込みによる新たな価値創出」に向けて、どんな分野で提案していけるかを検討する応用研究になります。 -

T.Ozawaさん
- 生成AIとはどのような性質を持つものなのか。まずそこからでした。ゼロからスタートして、ほぼ1年になります。あくまでも既存の生成AIを利用することでお客様に対してどんな新しい価値創造ができるかという応用研究が主旨にあり、生成AIそのものを開発しようというものではありません。
Q.生成AIの顧客適用に向けてのポイントは何でしょうか?
-

K.Yamamotoさん
- これまで AI の代名詞であった機械学習は、人間がインプットした情報を元に、学習・調整を経て、予測や特徴の検出を行いますが、生成 AI というのは、その情報から新たな解を文字通り生成する技術で、AI をより汎用的かつ簡単に用いることを可能とするものです。
-

R.Hoshinoさん
- 一般的な生成AIに質問を投げると、確かに答えは返ってきます。ただ、その知識のベースはAI自身が持っているもの、つまり開発元がトレーニングした常識やデータに基づいたものです。そのため、実際にAIを使うお客様ごとのニーズや利用シーン、企業の風土などは反映されていないんですよね。
-

Li.Sさん
- なるほど。だからこそ、実際の業務で活用するには、お客様ごとの状況や課題に合わせて、AIの使い方を工夫したり、応用研究を進める必要があるんですね。
-

K.Yamamotoさん
- はい、まさにその通りです。生成AIをそのまま導入しても十分な効果は得られません。お客様ごとの情報や現場の知見を組み込んだ上で、最適な運用方法やベストプラクティスを見つけ出し、本当に価値ある提案をしていきたいと考えています。
-

T.Ozawaさん
- 一方で、生成AIは厳密さや100点満点を求めるような回答には向いていないということが、今回の研究を通してわかってきました。
-

K.Yamamotoさん
- たとえばライン部品発注の数量決定に、生成AIがはじき出した結果をそのまま使うといった活用方法は現段階ではまだまだ難しいという感触です。
一方で、文章とか画像を作るという領域は生成AIが得意とするところなので、適用場面次第ではお客様の価値向上に使うことができそうですね。 -

T.Ozawaさん
- たとえばアイデア出しや文章の要約、情報抽出等に生成AIは、かなり使えると思っています。
それを元に、私たちが判断したり内容を詰めていく。そういった使い方をすれば、仕事の効率も上がりますね。
Q.スタートから1年。今後の目標は?
-

K.Yamamotoさん
- 今後は私たちからお客様に生成AIの具体的な適用に向けたプレゼンを行い、共同での研究開発に結びつけ、将来的には新しい価値共創することができたらと思っています。
-

T.Ozawaさん
- この1年で、技術を習得し、生成AIを使ったシミュレーションまで進みました。ここから先はシミュレーションなどで立てた仮説を、実際の現場で試して確かめていくことが大切になります。
たとえば、今注目されているRAG(拡張検索機能)をお客様に提案できるようにするためには、まず、対象となる企業固有の情報を学習させる必要があります。最終的な目標である新たな価値創造のためには、お客様との共同研究が必須で、今後はお客様の適用シーンを見つけていくことですね。
Q.つづいてソリューション研究開発部の Hさんと
Hさんと Lさんにお伺いします。最適化ソリューションを用いたプロジェクトとはどのようなものでしょうか?
Lさんにお伺いします。最適化ソリューションを用いたプロジェクトとはどのようなものでしょうか?
-

R.Hoshinoさん
- はじめに、前提となる数理最適化について説明します。数理最適化とは、与えられた制約条件のもとで、ある指標を最も良い結果にするように数式で表現し、システムとして構築していく手法です。例えば、「名古屋から豊田まで電車で移動する際、1000円以内、1時間以内、乗り換え2回以内という条件のもとで、最も早く到着できるルートはどれか?」といった問いに対して、最適な答えを導き出すシステムを考えるイメージです。
-

Li.Sさん
- 現在私は自動車生産ラインの計画立案に最適化を適用するプロジェクトにメンバーとして参画しています。
-

R.Hoshinoさん
 Lさんが関わっている生産計画立案プロジェクトは、
Lさんが関わっている生産計画立案プロジェクトは、 Lさんのような若手も入れて4名のチームで参画しています。メンバーそれぞれの役割は特に決めず、全員が同じ業務をこなせるチームです。仕事の状況に応じて、その都度担当を分担しています。
Lさんのような若手も入れて4名のチームで参画しています。メンバーそれぞれの役割は特に決めず、全員が同じ業務をこなせるチームです。仕事の状況に応じて、その都度担当を分担しています。
私はプロジェクトリーダーとして、重要なプロジェクトにも積極的に若手メンバーを参加させるようにしています。これは私だけでなく、当社の他のリーダーたちも同じ方針で取り組んでいると思います。
Q.具体的にはどのような内容でしょうか?
-

R.Hoshinoさん
- 生産計画の最適化は人手では難しく、多くの製造業が課題を抱えています。たとえば自動車メーカーでは、効率的かつ迅速な納車を実現するため、最適な生産・納車計画の策定が重要です。納車期間の短縮は、メーカーと購入者の双方にメリットをもたらします。
私たちは要件定義の段階からお客様と綿密に対話し、解決すべき課題を一緒に明確にすることに注力しました。今回はゼロからのシステム構築であったため、お客様自身も問題点を把握しきれていないケースも想定し、共に整理していきました。また、購入者からの声も参考にしながら、課題の抽出を進めました。 -

Li.Sさん
- お客様と会話する際には、お客様の意向や真意をくみ取る能力が求められると実感しています。この点が不十分だと、全く要望に沿わないことをやってしまう可能性もあります。
-

R.Hoshinoさん
- そうですね。そこは一番気をつけないといけない部分です。
このプロジェクトは2023年10月にリリースしました。そのうえでの課題や意見に基づいて2024年4月からブラッシュアップを開始し、2025年の4月に再度リリースしたところです。
どんなに満足度の高いシステムであっても、社会情勢等で、変更を余儀なくされることもあります。

Q.最後に皆さんにお聞きします。
研究開発やプロジェクトに携わることのやりがいや面白さ、今後の展望は?
-

R.Hoshinoさん
- 色々あると思いますが、横のつながりがある点がいいですね。自分たちのチーム以外の知見が必要な時には、他の部署との連携も珍しくないですし、プロジェクトによっては親会社である日鉄ソリューションズの「システム研究開発センター」のグループメンバーに参加してもらうこともあります。
-

K.Yamamotoさん
- 生成AIの応用研究では、とにかく、スタート地点もゴールも全て自分たちで設定するので、新聞や業界誌、海外事情等、手分けして情報を集めました。さらに「システム研究開発センター」の方にも随時加わってもらっています。そのあたりは、グループの強みですね。
いろいろな人の考えや技術に触れることは、自分自身の現状を見直すきっかけになり、刺激にもなりますし。 -

T.Ozawaさん
- グループとしてのスケールメリットはもちろん、私たちが関わらせていただくお客様は誰もがその名を知っている大企業ばかりです。規模が大きければ、既存のソリューションでは解決できない課題にアプローチできる機会も増えますね。
生成AIの研究開発に関して言えば、お客様との共同研究の実現を目指します。 -

R.Hoshinoさん
- 私たちも、最適化で培ってきた実績とスキルを武器に、今後は新たな業界にソリューション提供していきたいですね。
新規開拓のためにはゼロから探していく、提案していく姿勢が、より一層求められていると思います。 -

Li.Sさん
- いただいた仕事を遂行することも大事ですけれど、市場のニーズを把握しながら積極的に提案していくことが求められているのですね。
-

R.Hoshinoさん
- そうだと思います。自社ソリューション開発をはじめ、待っているだけではなく、自分から動かないといけないですね、これからは。
-
- お互いの研究を幅広い業界に提案していけるよう、これまで以上に連携を強めていき、この中部地方を盛り上げていきましょう!
その他プロジェクトを見る
You are the future itselfLet’s ENTRY
いろんな個性や能力を持った
あなたと働きたい。
KEYPERSONとしての一歩は
まず、ここからはじめよう!